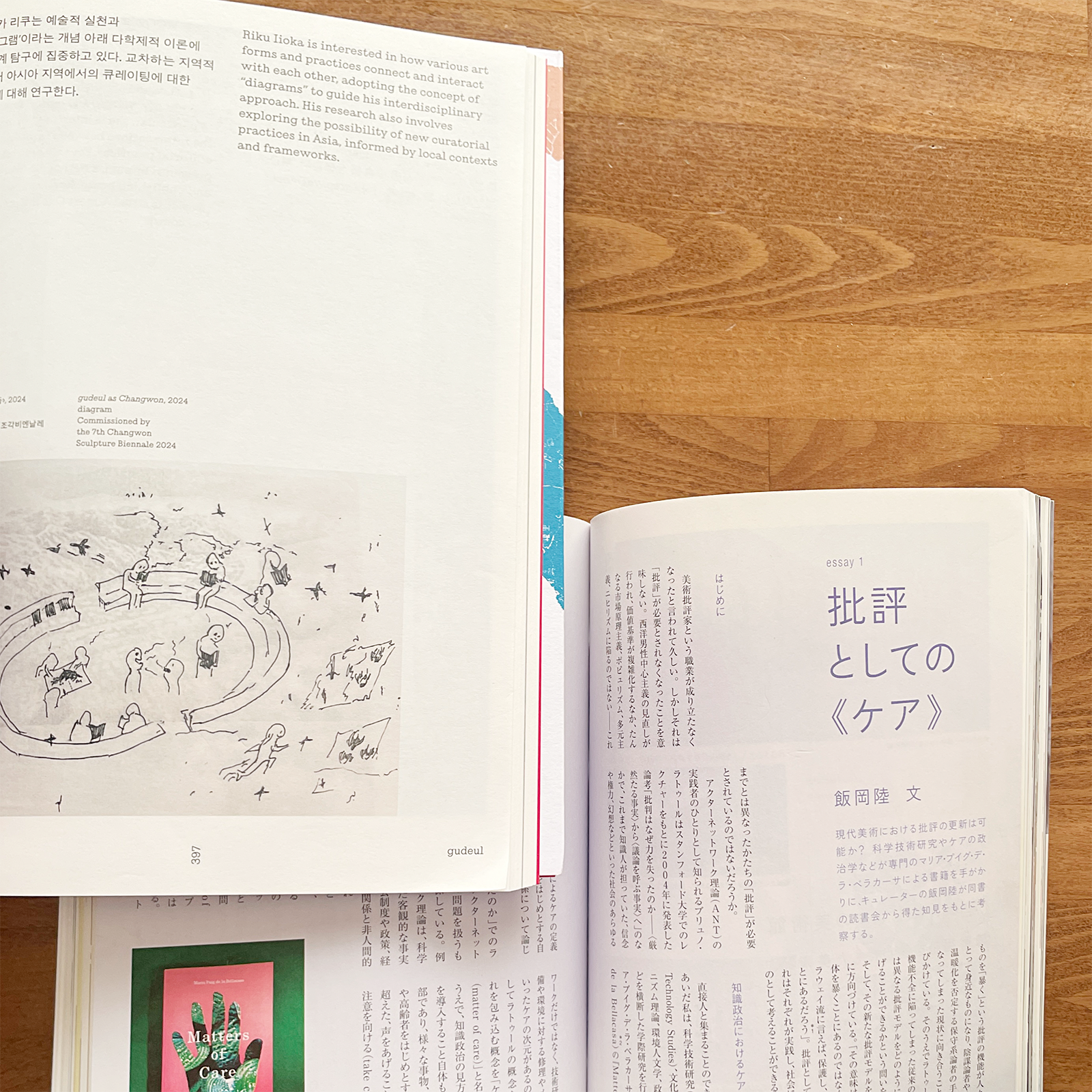出勤時・退勤時・あるいは昼食時に職員通用口のある西口を使うと、いつも風が吹いているんです。ただのビル風の可能性もありますが強風であることが多く、この風が海からやってきたものであると意識する時に、横浜を実感します。
他には私は散歩が好きなので、休日を使って横浜市のいろいろなところを散策するようにしています。
三溪園に足を運んだり、アーティストを誘って野毛山動物園や横浜市歴史博物館に行ってみたり、中華街で朝からお粥を食べたり、鶴見川沿いや、港南台駅から鎌倉まで抜けるハイキングコースをひたすら歩いたり。あとはそこに住む人たちを想像しながら住宅地を歩くのも好きですね。これらは人々の生活や社会、歴史とのつながりから現代美術を扱おうと考えている自分にとってのインスピレーション源にもなっています。